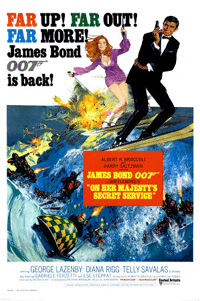
|
女王陛下の007
1969 イギリス 140分 |
||
|
監督/ピーター・ハント
出演/ジョージ・レーゼンビー ダイアナ・リグ テリー・サバラス |
|||
| 海辺のワインディングロードを車で走るジェームズ・ボンド(ジョージ・レーゼンビー)。すると1台の車がクラクションを鳴らし、ボンドの車を抜き去って行った。しばらくボンドが走ると、先程抜き去って行った車がドアを開けたまま、誰れも乗っていない状態で止まっていた。 |
それは個人的な問題だ
原作はイアン・フレミングの小説。映画007シリーズの第6作目となる作品。
数多くの作品からなる007シリーズの中でも特に異色な作品だと言えるだろう。その理由は、ひとえにジェームズ・ボンドを演じているのがジョージ・レーゼンビーだからである。本作では、それまで務めてきたショーン・コネリーからレーゼンビーへのボンド役の交代が実施されている。
ボンド役の交代は本作が初めて。ただ、公開当時はインパクトがあったとしても、後に何度も繰り返されている事を考えれば、ボンド役の交代自体は今となっては不思議でも何でもなく、むしろ予定調和だ。但し、他の俳優が複数作ボンド役を演じているのに対し、レーゼンビーは本作1本のみ。その事が本作の異色感を強くしているのだろうし、もっとハッキリ言えば、本作の疎外感を生み出していると思う。
ただ面白い事に、疎外された異色作であるにもかかわらず、後の007作品で取り上げられる事柄の数々のオリジナルが所在する作品でもあるだ。例えば第19作に登場し、作品タイトルにもなった「ワールド・イズ・ノット・イナフ」の言葉の起原は本作にある。そういった意味でも不思議な位置付けの作品だと言えるだろう。
ジェームズ・ボンドは、自殺でもするかのように海に入水しようとしている女を助けた。だが、その時に突如として2人組の男が現れ、女を連行しようとし、ボンドに襲い掛かった。2人を片付けるボンド。但し、女もその場から逃げてしまった。女を追ったボンドは、ホテルで女の車を見つけ、そのホテルに滞在する。そこでボンドは、カジノでの負けを肩代わりする事で、その女、トレーシーと親密になり、一夜を共にする。しかし、ボンドが目を覚ますと、またもやトレーシーはいなくなっていた。トレーシーの代わりに現れたのは複数の男たち。男らは銃を突き付けボンドを拉致する。ボンドを連れてくるように指示したのはヨーロッパ有数の犯罪組織ユニオン・コルスの首領ドラコ。何とドラコはトレーシーの父親だった。更に驚く事にドラコは、自暴自棄のトレーシーを立ち直らせる為にボンドにトレーシーと結婚して欲しいと頼むのだった。
コネリーからレーゼンビーへの交代の理由がポジティブなものなのか、それともネガティブなものなのか私には分からない。ただ、いずれにせよ、この機会をカンフル剤としてシリーズのムードを一新、そこまで行かなくても修正・変更しようとする意図、具体的には特化してしまったファクターを是正し、スパイアクションの本来の姿に立ち返ろうとする意図が伺える作品である。
特化してしまったファクターとは大まかには2つ。まず1つは秘密兵器だ。秘密兵器は007の売りである。しかし、次第にエスカレートして大掛かりになり、その事が荒唐無稽な作風を増長させているように感じる。
本作には大掛かりな秘密兵器は登場しない。大切な売りを排除した事は大きな痛手なのかも知れないが、その痛手と引き換えに多少の名残はあるもののストイックな印象を取り戻し、スパイアクション本来の醍醐味を感じさせる事に成功していると思う。
もう1つの特化してしまったファクターとはコネリーである。007シリーズがコネリーをブレイクさせたのは言うまでもない。だが逆に、コネリーが007シリーズをメジャーにしたという見解も当てはまるのではないかと思う。
コネリーは匂い立つようなフェロモンを発して原作の設定以上の存在感をボンドに与えた。そのボンドのキャラクターが魅力となり、007シリーズを牽引してきたのは間違いないだろう。
但し、あまりにも存在感が強すぎて、すべてがコネリー色に染まってしまった感があるのも否めない。率直に言って、本作のボンド、レーゼンビーは存在感の上ではコネリーに見劣りする。ただ、その事で他のファクターとのバランスがとれて作品全体を見渡せるようになっていると思うし、ひいては本来の007の資質が感じられる造りになっているように思う。
レーゼンビーはコネリーのような強烈で濃厚な存在感は示せていないが、若さを武器に爽やかでスマートな印象をボンドにもたらしている。そのボンドの方が原作のボンドに近いような気がする。そして明らかにコネリーのボンドよりも勝っている面がある。それはアクションに関してである。
何でもレーゼンビーはアクションの素質を買われてボンド役に抜てきされたと聞く。その情報の信憑性を裏付けるかのようにレーゼンビーは素晴らしいアクションを魅せる。演出の妙も相まって、レーゼンビーの生身のアクションは、それまでのシリーズにはなかったダイナミズムをもたらしている。
本作の、ちょっとミステリアスで気を持たせる冒頭のシーンは新しい章の幕開けを感じさせる。しかし、結果として幕開けにならなかったのは誰もが知るところである。
本作以降もレーゼンビーがボンドを演じていたら、007シリーズが現実どおりに繁栄していたかどうか、私には見当がつかない。しかし、ウイットは残しつつも割と骨太で完成度の高いスパイアクションシリーズが展開されたのではないかとの想像は過る。そう考えると1作でレーゼンビーが降板したのは、あまりにも惜しい。
レーゼンビーがボンドを演じている事に加えて、ストーリーもシリーズの中ではユニークであるので本作がイレギュラーな007作品であるのは間違いない。但し、007の真実、そして007に対する理想と情熱が詰まっている作品だと感じる。
そう考えると、ちょっと視点を変えてみれば、早すぎた「カジノ・ロワイヤル」という解釈も出来るのではないかと思う。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★