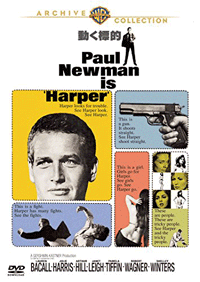
|
動く標的
1966 アメリカ 121分 |
||
|
監督/ジャック・スマイト
出演/ポール・ニューマン ローレン・バコール アーサー・ヒル |
|||
| 目覚まし時計を止めてベッドから出たハ−パー(ポール・ニューマン)は、点けっぱなしだったテレビを消し、窓のブラインドを上げ、冷蔵庫から氷を取り出した。洗面所に行き、洗面器に水を溜めて氷を全部入れるとハ−パーは洗面器に顔を突っ込んだ。 |
バカね、こんな朝食作って
失踪した大富豪の行方を捜索する探偵の姿を描いたミステリー。原作は、ロス・マクドナルドの小説。続編に1975年公開「ハーパー探偵シリーズ/新・動く標的」がある。
マクドナルドは、ダシール・ハメット、レイモンド・チャンドラーの後継者とされるハードボイルド小説作家であり、マクドナルドが創造したリュー・アーチャー(リュウ・アーチャーと記載されている場合もある)は、ハメットのサム・スペードやチャンドラーのフィリップ・マーロウと同様のハードボイルド・ヒーロー。そして本作の原作小説は、そのアーチャーが長編小説において初登場する作品だ。
しかし、本作の主人公の名前はリュー・アーチャーではなく、ルー・ハーパーに変更されており、邦題こそ原作小説と同名だが、原題は「ハーパー(Harper)」に変更されている。何でも、「ハスラー(The Hustler)」「ハッド(Hud)」とニューマンの主演する「H」で始まるタイトル作品が好評だった為、「ハーパー」にタイトルが変更されたらしい。但し、原作者のマクドナルドがリュー・アーチャーという名前の権利を保持したかったので、名前の変更を余儀なくされたという説もある。
タイトル変更に伴ってか、ストーリーにもアレンジが加えられているが、本筋は概ね原作小説を踏襲しており、ミステリーとして見応えのある内容になっている。
昔馴染みの弁護士、アルバートに紹介されて私立探偵のハーパーはサンプソン家を訪れる。そこでハーパーはサンプソン夫人と面会し、蒸発した夫の居所と夫と一緒にいる人物を知りたいとの依頼を受ける。蒸発したのは昨日で、ラスベガスからロサンゼルスに戻ったのだが、空港で自家用飛行機のパイロット、アランをまいて消えたという。サンプソン夫人は詳しい話はアランに聞き、報酬に関してはサンプソン家の顧問弁護士であるアルバートと話すようにと言うので、まず、ハーパーはサンプソン家のプールにいたアランに会いに行く。プールにはサンプソン家の長女、ミランダもおり、ミランダはサンプソンの後妻であり、自分とは血の繋がりのない継母のサンプソン夫人への不満を口にするのだった。サンプソン蒸発時の状況を聞いたハーパーはアランとロサンゼルスに行く事になる。その前にアルバートの事務所に向かうハーパーは、車中、アランからアルバートとミランダとの間に縁談がある事を聞く。そしてアルバートに会ったハーパーは、アルバートが24歳も年下のミランダにメロメロになっている事を知る。
本作の冒頭、ハーパーが仕事の依頼を受けるシーンでサンプソン夫人はハーパーに「何か飲む?」と酒を勧めるのだが、ハーパーは「朝からは…」と言って断る。それを受けてサンプソン夫人は「探偵でしょ?」と言うのだが、ハーパーは「新しい型」だと答える。これは原作小説にもあるやりとりであり、原作小説の日本語訳では「わたしはこれでも新しい型(タイプ)の探偵なんです」となっている。この「新しい型」というのが、本作の根底にあると私は考える。
では、「古い型」は何かというと、ハンフリー・ボガートがスペードやマーロウ等を演じる事を通じて世間に広めたハードボイルド・スタイルだ。つまり、本作は大げさに言えば、ボガートにケンカを売っているという事になる。本作公開時はアメリカン・ニューシネマが産声をあげようとしている頃なので、既存のハードボイルドに一石を投じるという気概があってもおかしくはない筈だ。
余談だが、前述したとおり「新しい型」というのは原作小説にあったセリフなので、原作者のマクドナルドはハメット、チャンドラーの後継者だと言われつつも、彼らをトレースするだけの作品を執筆するつもりではなかったであろうという事も推測できる。
本作における「新しい型」の具体例をを挙げると、本作でニューマンはボガートの代名詞、タバコを吸っていない。その代わりと言わんばかりにガムを噛んでいるのだから、どうしても意識していると感じてしまう。
もっと顕著なのは、カッコ悪い姿をあからさまにしている点だ。ゴミ箱に捨ててある出がらしのコーヒーを飲む姿や、塗装が剥がれたオンボロ車を乗り回す姿は、寸分の隙もなかったボガートのハードボイルド・スタイルとは明らかに対極に位置している。
だが、ニューマンのカッコ悪い姿は味があって俄然、魅力的なのだ。ハードボイルドの原則からすると、ボガートのスタイルが正解。ニューマンのスタイルはハードボイルドとは呼べないのかも知れない。しかし、後の時代の状況を鑑みると、ニューマンのスタイルはハードボイルドとして受け入れられたと考えられる。それどころか解釈によっては、ハードボイルドの主流になっている。何せ巷では、カッコ悪い部分も含めてカッコ良いとされる、オフビートなハードボイルドで溢れ返っているのだ。
もっとも、カッコ悪い姿をカッコ良く見せるのは至難の業であって、誰にでも出来る芸当ではない。ニューマンの役者としてのセンス、技量の高さが伺える。そんな事もあってか、本作は世間一般では、ニューマンの代表作とは言えないかも知れないが、知る人ぞ知る人気作品のようだし、ハードボイルドをこよなく愛する人達にも高評価を得ている作品のようだ。
さて、ハーパーのオンボロ車なのだが、これは356という車種のポルシェで、あのジェームズ・ディーンも一時所有し、レースにも参戦していたという高性能なスポーツカーだ。但し、本作公開当時には、すでに356は型遅れになっていたので、当時は安価で購入出来たという話もある。なので、オンボロな事は珍しくなかったのかも知れないのだが、とは言ってもポルシェはポルシェであり、あえてポルシェをを選んだ事はカッコ悪さだけを強調するつもりはないという意図が伺える。
ちなみに作家の村上春樹はポルシェのボクスターがお気に入りで、何台か乗り継いで所有しているらしい。比較的軽量でコンパクト、オープントップのボクスターは356を彷彿とさせるとも言って良いポルシェだが、村上は高校時代に本作を10回観ているとの事なので、ボクスターへのこだわりは、本作の影響があるのかも知れない。
それは、さて置き、このポルシェ、結構、登場シーンが多く、カーチェイスのようなシーンもある。ご存知、ニューマンはカーレーサーでもあり、日産スカイラインのイメージキャラクターをしていた事もあった。もっとも、ニューマンがカーレーサーになるのは本作以降の事だが、それでもニューマンのドライビングシーンを多く堪能出来るのは、得した気分だ(但し、背景の合成は多用されている)。
ジャネット・リーやシェリー・ウィンタース等、出演陣が豪華な事も本作の特徴だ。ニューマンの出演が叶わなかった「エデンの東」のヒロイン、ジュリー・ハリスが出演していたりもする。そんな中、ローレン・バコールの出演が私には興味深かった。ボガートがマーロウを演じた「三つ数えろ」に出演し、そればかりかボガート夫人でもあったバコールなので、次世代のハードボイルド探偵を母親のような立場で見守っているように感じた。
後に「タワーリング・インフェルノ」で共演をするスティーブ・マックイーン主演の「ブリット」を比較対象とするのは有意義な事ではないかと思う。比較するだけではなく、ニューマンがブリットを演じたら、逆にマックイーンがハーパーを演じたらなんて事を想像するのも楽しいのではないか。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★