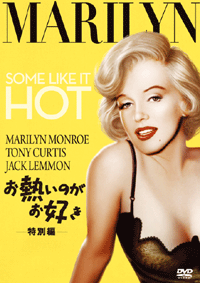
|
お熱いのがお好き
1959 アメリカ 120分 |
||
|
監督/ビリー・ワイルダー
出演/トニー・カーティス ジャック・レモン マリリン・モンロー |
|||
| 夜のシカゴの街を1台の霊柩車が走っていた。するとサイレンを鳴らしたパトカーが霊柩車の後に付いた。スピードを上げる霊柩車。パトカーに乗った警官たちは霊柩車に向けて発砲する。時は1929年、禁酒法の時代。霊柩車に積まれた棺の中には、大量の酒が隠されていたのだった。 |
泣かないで、男のためになんか
事情があって女だけのバンドに、女装をして潜り込んだ男2人が巻き起こす悲喜こもごもな珍騒動を描いた作品。
マリリン・モンローの視覚的な一番のイメージは「七年目の浮気」での白いドレスのスカートがまくれ上がるシーンだろう。では、聴覚に働きかけるイメージは何か? それは甘い囁きの“ブプッピドゥ”ではないかと思う。本作は、その“ブプッピドゥ”が含まれる楽曲「I Wanna Be Loved By You(あなたに愛されたいの)」が登場する作品である。
禁酒法が施行されている1929年のシカゴ。スパッツが率いるマフィアは、葬儀場を隠れみのにして、裏側で酒を出すナイトクラブを経営していた。ある日、繁盛しているナイトクラブに警察の摘発が入る。サックス奏者のジョーとベース奏者のジェリーは、ナイトクラブに出演しているバンドの一員であり、摘発の場に居合わせていたのだが、摘発の直前で警察の存在に気付き、検挙を免れるのだった。だが、ジョーとジェリーは仕事がなくなってしまった。そこで、馴染みのエージェントを訪ねる事にした。丁度エージェントは、フロリダで3週間働けるサックス奏者とベース奏者を探している最中。だが、それは女性だけで構成されるバンドの為のものであり、もちろん女性でなければならなかった。その条件の良さからジェリーは女装して働くと主張するのだが、認められる筈もなく、ジョーとジェリーは代わりに一晩だけの仕事、イリノイ大学のバレンタインパーティーの仕事を得るのだった。イリノイ大学に行く為にエージェントの事務員ネリ−から車を借りる事にしたジョーとジェリーが、ネリ−が車を預けているガレージに行くと男たちがカードを楽しんでいた。そこにスパッツ率いるマフィアが現れた。スパッツは、カードをしていたチャーリーが摘発されたナイトクラブの事を警察に密告したのだと思っており、その場でチャーリーたちを射殺する。その時、ジョーとジェリーは隠れていた。だが、見つかってしまい、スパッツはジョーとジェリーも殺そうとする。しかし、間一髪のところで逃げ出す事に成功するのだった。だが、ジョーとジェリーはスパッツに顔を知られており、この先、追われる事は目に見えていた。そこでジョーは、先ほどのエージェントに電話をし、女性の声色で女性バンドに入りたい旨を伝える。エージェントを騙してバンドへの加入を認められたジョーとジェリーは、女装して女性に成り済まし、女性バンドのメンバーと一緒に汽車でフロリダへと向かうのだった。
本作はモノクロフィルムで製作された作品である。そうなった理由はカラーフィルムで製作する費用がなかったからではなく、トニー・カーティスとジャック・レモンの女装姿の無気味さを和らげる為の措置だったらしい。公開当時の世間のモラルの基準が伺える、貴重なエピソードだと思う。
だが、そういった配慮が表現力、そして伝達力の領域を狭めているのは事実であるだろう。モノクロよりもカラーの方が表現力も伝達力も優れているのは言うまでもない。その影響を一番受けたのはマリリン・モンローであるだろう。ルックスはモンローの大きな武器。本作ではモンローのブロンドの髪も赤い唇も楽しむ事は出来ない。
しかし私は、悪い事ばかりではないと思う。むしろ良い影響を与えているのではないかと思う。色がないからといってモンローのセクシュアルな魅力が封印された訳ではない。だが、幾分かは中和されている。そこで浮き彫りになるのがモンローのチャーミングな部分。モンローが、いかに可愛らしい女優であったか本作を観れば実感出来るだろう。
但し、ストーリーはモンローというよりも、カーティスとレモンが中心となっている。ただ、この2人のコンビが最高なのである。女装をしながらも二枚目風情を匂わせるカーティスと、あくまでも道化な役回りに徹するレモン。振り回されるレモンは少し気の毒にも感じるのだが、それこそが本作のコメディーの源である。
奇妙な設定のドタバタコメディーが所狭しと繰り広げられる。その中でも確かに感じる男2人の友情。更にはモンローとのロマンスも加わり、贅沢、且つ極上のエンターテインメントが紡ぎ出されている。
ちなみに、本作をきっかけにレモンはビリー・ワイルダー監督作品の常連となり、名作「アパートの鍵貸します」が生まれている。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★