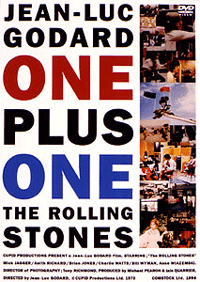
|
ワン・プラス・ワン
1968 イギリス 100分 |
||
|
監督/ジャン=リュック・ゴダール
出演/ザ・ローリング・ストーンズ |
|||
| レコーディングスタジオで、ミック・ジャガーとブライアン・ジョーンズが互いに向き合い、ギターを鳴らしながら曲のアイデアを出し合う。そのギターに合わせてチャーリー・ワッツがドラムを叩く。ビル・ワイマンはベースを抱えて待機する。その輪の中にキース・リチャードが加わる。 |
変革の時代、加速し始めた石たち
ザ・ローリング・ストーンズのレコーディング風景のドキュメンタリーと、当時の世情や主張を描いたセミドキュメンタリー風のドラマを交錯させて映し出した作品。
まさに時代を切り取った作品なのではないかと思う。当時は公開年に起きたフランスの五月革命にも象徴されるようなカウンターカルチャーの時代。ワンカットで力強く押し進められるドラマ部分は、その事を色濃く物語っている。
ストーンズのレコーディング風景に関心が集まるであろう本作ではあるのだが、製作時期を考えると、あくまでも想像ではあるが、もしかしたらストーンズの起用は、反体制のシンボルとして、安易に作品を賑やかす目的の為だったのかも知れないなどと推測してしまう。
しかし、結果的に本作でのストーンズのドキュメンタリーは、ストーンズファンのみならず音楽界にとって重要な記録となっている。
その要因として、まず挙げられるのが、本作で描かれているのが、アルバム「ベガーズ・バンケット」のレコーディング風景である事である。このアルバムは、ストーンズが世界最高のロックバンドとしての地位を確固たるものとする黄金期の幕開けとなる作品である。実際、「ベガーズ・バンケット」を皮切りとした、後に続く何作かはストーンズの中でも最も評価の高いアルバム群である。
次に、そのアルバム製作の中でも「悪魔を憐れむ歌」のレコーディング風景がメインとして収められている事が挙げられる。ストーンズの代表曲は数多くあるのだが、その中でも最重要のひとつであり、ストーンズのミステリアスな部分のイメージを担っているのが「悪魔を憐れむ歌」である。
ロックという観点から捉えれば、ユニークにも思えるサンバのようなリズムを用いている独特な楽曲が、さすがに始終とはいかないものの、ある程度、どういった経緯で作り上げられていったのかが分かるレコーディング風景の記録は、大変貴重で価値があると言えるだろう。
そして、初期のストーンズの中心人物であったブライアン・ジョーンズの姿が収められているのも重要なポイントである。本作冒頭では確認出来る彼の姿は、最後には確認出来なくなる。ドラッグに溺れた彼は、この撮影期間中にストーンズを脱退する。そして、脱退からほぼ1ケ月後に謎の死を遂げる。本作と時が重なるブライアン・ジョーンズの最期の日々は、ブライアン・ジョーンズ ストーンズから消えた男に詳しく描かれている。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★
おすすめ映画情報-シネマメモ