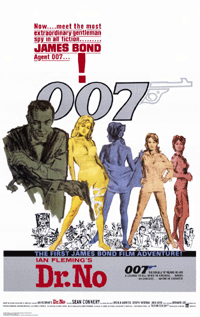
|
007/ドクター・ノオ
1962 イギリス 105分 |
||
|
監督/テレンス・ヤング
出演/ショーン・コネリー ジョセフ・ワイズマン ウルスラ・アンドレス |
|||
| ジャマイカの会員制のクイーンズ・クラブでカードゲームをしていたストラングウェイズ(ティム・モクソン)が中座し、自分の車に戻ったところ、三人組の男に射殺されてしまった。 |
007は殺しの番号
原作はイアン・フレミングの小説。映画007シリーズの第1作目、世界一有名なアンサングヒーロー、ジェームズ・ボンドのスクリーンデビューとなる作品である。
本作は映画としては1作目なのだが、フレミングの原作小説では007シリーズの6作目にあたる作品である。ジェームズ・ボンドがコードネーム007のスパイとなる経緯は、ずっと後年、2006年に公開されたダニエル・クレイグがボンドを演じたシリーズ第21作「カジノ・ロワイヤル」で描かれている。
但し、それは映画化の際の脚色であり、フレミングの原作小説の「カジノ・ロワイヤル」では1作目でありながらも、すでにボンドは経験値の高いスパイとして登場している。なので、原作6作目が映画化1作目であっても、あまり支障はないだろう。
ちなみに、作品タイトルの「ドクター・ノオ」は原題そのままなのだが、日本初公開時の邦題は「007は殺しの番号」だった。日本で「ドクター・ノオ」と作品タイトルを改めたのは1972年にリバイバル公開された時からである。
イギリスの秘密情報機関MI6の本部に入るジャマイカ支局からの通信が突如として途絶え、現地支局員のストラングウェイズとその秘書の行方が分からなくなった。ストラングウェイズはアメリカ当局の要請でアメリカの空軍基地及び宇宙センターがあるフロリダ州のケープ・カナヴェラルへの妨害電波を調査中だった。それは、先にアメリカが南大西洋へ発射したミサイルが妨害電波によりブラジルの密林に落下した事を受けての、次に予定されている月ロケットの打ち上げを妨害される事なく成功させる為の調査だった。この異常事態にMI6は敏速に対応。ロンドンのアンバサダー・クラブでプライベートを勤しんでいた00課の諜報員、007/ジェームズ・ボンドを午前3時に急遽本部に召集し、事の真相を究明すべく午前7時の航空便でジャマイカへと派遣するのだった。
率直に言って本作は、残念ながら古さを感じさせる面が往々にしてある作品である。ラブストーリーやヒューマンドラマなら時代を超えた普遍性を感じるのかも知れないが、ことスパイ作品、とりわけ本作のような派手なスパイアクション作品では、時の流れは残酷と思える程にマイナスに影響を及ぼしてしまう。
なので、今日のスパイ作品、スパイアクション作品と正面切って比較するのは明らかに分が悪い。その事は予め心して本作に臨むべきだろう。ただ、視点を変えてみれば、今日までにエンターテインメントが、いかに進化したかを感じる事が出来るだろう。
但し、だからといって見どころがない訳ではない。残酷な時の経過を逆手にとってクラシカルな味わいを堪能する事も出来るだろう。確かに今日のスパイ作品、スパイアクション作品の完成度は全般的に高水準である。しかし、そこを突き詰めた故に失われた生々しい真髄は、本作には息づいていると言えるだろう。
そして何と言っても本作の最大の価値は、映画007シリーズの記念すべき第1作である事だ。
後に何年にも渡って繁栄し続ける黄金シリーズの第一歩である事はもちろんだが、それ以上の本作の多大なる功績は、多くのフォロワーを生み、エンターテインメント界に絶大な影響を与えた事だろう。前述した今日のスパイ作品、スパイアクション作品との比較も本作が存在したからこそ、すなわち本作を起源にジャンルが発展したからこそなのである。
後世に道を開いた原因は、ダイナミックな物語の展開力もさることながら、ジェームズ・ボンドのキャラクターに因るところも非常に大きいだろう。
ボンドは抜群の運動神経を誇り、肉体的にも精神的にもタフであり、頭脳明晰で博学なインテリであり、洗練されたセンスが備わった完全無欠なスーパーマン。但し、慈悲深い聖人君子な正義漢ではなく、任務の為には非情に徹する真のプロフェッショナルでもある。更には洒落たユーモアセンスに代表されるように、どこか脱力した大人の余裕も併せ持っている。これ程の男が魅力的に映らない訳はないだろう。
しかもボンドはショーン・コネリーと出会って、その魅力を昇華させた。コネリーのそれまでのキャリアを考えればボンド役は大抜擢のように感じるのだが、見事なまでに正解を引き当てたと言えるだろう。もちろんコネリーにとってもプラスなのは言うまでもない。
30歳は過ぎてるとはいえ、この貫禄はただ者ではない。ニューフェイスであるなら尚更だ。更には、セクシーなワイルドさが溢れんばかりに漲っている。この規格外の才能が、品良くスーツを着こなした事でボンドは完成したのだ。
何でも、原作者のフレミングは田舎者風情なコネリーのボンド役には反対だったらしいのだが、テレンス・ヤング監督自らコネリーを自分の行きつけのテーラーに連れて行き、立派な英国紳士へと仕立てたらしい。ボンド引退後、年々渋味を増すコネリーも魅力的だが、トラッドに身を包み、その隙間から雄々しいフェロモンを発している若きコネリーも匂い立つ程に魅力的である。
また、007シリーズには伝統として、いくつかの決まり事、フォーマットがあるのだが、その多くが1作目にしてすでに出来上がっている事に感心させられる。
本作を製作するにあたりシリーズ化は目論んでいたのだろうが、それも本作の出来次第、評判次第であった筈だろう。だからこそ出来る限りの英知を注ぎ込んだのだろうが、それでも今後の展望が分からない状況、もっと踏み込んで言えば、制作費が100万ドルという低予算からも分かるように、期待薄との烙印が押されてしまっているとも思える状況で、後に誰もが知るところとなるジェームズ・ボンドのテーマ曲をはじめ、多くの007スタイルが本作で完成されている事には驚き覚えるし、また、嬉しくも思う。
その有名なテーマ曲を用いたモーリス・ビンダー作のオープニングのタイトルバックが秀逸。007の代名詞となるガンバレルの覗き穴から始まり、特に転調するまでのカラフルなドットがグラフィックイコライザーのディスプレイであるかのようにテーマ曲に反応する様子は、辿り着けそうで辿り着けない至極の様式美だ。
技術を手にし、可能性を広げる事は大切だろう。だが、なまじ技術力で体裁が繕えてしまうと、本質を深く掘り下げる行為を怠ってしまうきらいもある事だろう。アイデアを極限まで煮詰めた、シンプル・イズ・ベストの極みのようなタイトルバックは、豊かな時代に忘れ去られた大切な原点を思い出させてくれるように思う。それは本作の今日の在り方そのものだと言えるのかも知れない。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★