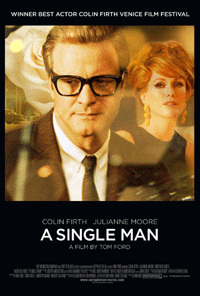
|
シングルマン
2009 アメリカ 99分 |
||
|
監督/トム・フォード
出演/コリン・ファース ニコラス・ホルト ジュリアン・ムーア |
|||
| 雪道に滑った車が転覆しており、その車から飛び出すかたちでジム(マシュー・グッド)が死んでいた。ジョージ(コリン・ファース)は亡骸となったジムに歩み寄り、ジムの唇にキスをした。 |
恐ろしいなりの美しさがある
原作はクリストファー・イシャーウッドの小説。恋人を失った同性愛者で大学教授の男性の、ある1日を追った作品。
監督のトム・フォードは、言うまでもなく著名なファッションデザイナー。1990年代に老舗ファッションブランド、グッチを一大ムーブメントを巻き起こして再建して一躍名声を得て、更には同じく老舗のイヴ・サンローランも手掛け、その後、独立して自身のブランドを立ち上げたファッション業界の最重要人物。本作は、そのフォードの監督デビュー作である。
同性愛者のジョージは、16年間を共にした恋人のジムを自動車事故で失った。事故から8ケ月後の1962年11月30日、金曜日の朝、大学教授であるジョージは、いつものように勤務先の大学へと向かう準備をしていた。その最中、チャーリーから電話が入る。チャーリーはジョージの昔からの友人。その電話でジョージは今夜訪ねたいと申し出る。その申し出にチャーリーは快諾するのだった。今朝のジョージの出勤準備には、いつもとは違う行動が含まれていた。それはデスクの鍵の掛かった引き出しにしまってあった拳銃を取り出し、持っていくバッグに入れた事。そして使用人のアルヴァに、いつも以上に感謝を示した事だった。
本作は、アメリカのテレビドラマ「マッドメン」と同じプロダクションデザインチームが手掛けた作品だという。「マッドメン」は1960年代のニューヨークの広告業界を描いた作品であり、大人好みな渋いストーリー展開もさる事ながら、緻密でムードある時代描写から、映像クオリティーも評判高い作品である。
確かに本作は「マッドメン」と同じ時代を舞台にしている。だが、私には扱うテーマ、そして業種や土地柄、更には演出の方向性が異なっているからか、必ずしも共通したムードだとは感じなかった。だが、それでも本作が高いクオリティーの映像を誇っているのは確かである。
そもそも「マッドメン」を持ち出すまでもなく、フォードの監督作品なので美意識が高い作品であるのは当然だろう。衣装はもちろんの事、家や車等々、本作に登場する、ありとあらゆるもの全てがスタイリッシュだ。また、描かれている内容がホモセクシャルについてだという事も、美意識が高いと感じる要因になるだろう。
ただ、本作の真に秀でたところは、大衆に意識が向いている点だと思う。こういったタイプの作品は、独りよがりにアート性を追求してしまうきらいがある事だろう。そして、それを理由に難解に陥ってしまう場合もある事だろう。だが本作は、大衆性を蔑ろにしてはいない。だから意味不明で考え込んでしまうような作品ではない。また、高い美意識というのも、実のところ大衆性があるからこそ実感出来るのだと思う。
そういったバランス感覚も、フォードの持つ優れたセンスであるだろう。フォードが作ってきた服が、いくら優秀なデザインだったとしても独りよがりに溺れ、独創性ばかりに走る代物であったのならば、それはそれでデザイナー、あるいはアーチストとしての評価が得られたのかも知れないが、大ヒットまでには至らなかっただろう。
フォードの服が大ヒットした一因には大衆への意識が必ずあった筈。そういった総合的なセンスが、そもそもフォードに備わっていたのか、それともファッションデザイナーをしているうちに身についたのかは分からないが、いずれにせよ、本作で発揮されている事は間違いない。
本作を観て私が思い出したのは「ベニスに死す」だ。取り扱ったテーマの類似性もさる事ながら、自身のアーティスティックな主張を一般的な感覚に浸透させる、客観性を有した優秀な表現力がある点も似ているように思う。そんな事から、もしかするとフォードは、ルキノ・ヴィスコンティと同じような資質を持ったクリエイタ−なのではないかと思ったりもする。
フォードに今後も映画監督を続ける意向があるのか、私は知らない。また、本作のような作風を時代が許してくれるのかも私には分からない。ただ、本作を観る限り、フォードの映画界での次の活躍を期待したくなる。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★