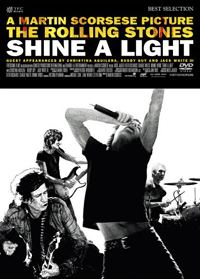
|
ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト
2008 アメリカ 122分 |
||
|
監督/マーティン・スコセッシ
出演/ミック・ジャガー キース・リチャーズ チャーリー・ワッツ ロン・ウッド |
|||
| マーティン・スコセッシのコンサートプランに悪態をつくミック・ジャガー。対するスコセッシも、そんなミックの態度に不満をこぼす。 |
60歳になっても続けてると思う?
2006年にニューヨークのビーコン・シアターで行なわれたローリング・ストーンズの慈善コンサートの模様を、舞台裏や過去のインタビュー映像等を交えて収めたドキュメンタリー作品。作品タイトルは1972年にストーンズがリリースしたアルバム「メイン・ストリートのならず者」に「ライトを照らせ」との邦題で収録されている楽曲と同名。
何と言っても本作最大のポイントは、世界最高のロックバンド、ストーンズと映画界の巨匠マーティン・スコセッシとの豪華で強力なタッグであるだろう。
スコセッシはザ・バンドの解散コンサート「ラスト・ワルツ」を映画化したり、マイケル・ジャクソンの「BAD」のミュージックビデオを演出したりと音楽に造詣が深い映画監督として知られている。
ならば殊更、同世代のトップランナー、ストーンズには思い入れがあったのではないかとの想像は禁じ得ない。実際、「ディパーテッド」では「ギミー・シェルター」が使われている。そんな巨匠が手掛けたライブ映画なので、さすがに普通のドキュメンタリー作品にはなっていない。
驚いたのは、作品の冒頭、コンサート直前にアメリカ合衆国の元大統領ビル・クリントンと妻のヒラリーが登場し、ストーンズのメンバーと交流している場面が収められている事だ。元職とはいえ体制側のシンボルであるアメリカ合衆国大統領と、不良性が持ち味の反体制側のシンボル、ストーンズとの交流は異様な光景のように思える。
もっとも、ストーンズの不良性とはビジネス的な側面が往々にしてある事だろう。そもそもストーンズは、そのイメージとは裏腹に中産階級出身だと聞く。とかくビートルズと比較されるストーンズであるが、ビートルズが労働階級出身であるのとは実に対照的だ。
ストーンズが醜悪なスキャンダルに塗れたのは紛れもない事実。だが、それを肥やしとし、逆手にとって上手く利用し、バンドを運営・発展させた賢さがあるのも事実だろう。本当のならず者だったとしてら、ここまで大きな成功は収められなかった筈である。
地位も名声も巨万の富も手にしているストーンズ。ミック・ジャガーに至っては、事もあろうにナイトの称号までも手に入れている。そんなストーンズが反体制だと言えないのは分かっている。だが、それでも本来ならクリントンとの交流は見せてはならない光景だったのではないかと思う。
スコセッシの意図はどこにあるのか? 成功者として称えようとしているのか? それともメッキを剥がそうとしているのか? その真意は測りかねるが、いずれにせよ価値あるシーンであるだろう。そんな中、ストーンズのメンバーがヒラリーの母親を労るシーンは、すべてを超越した美しさを感じさせる。
興味深いバックステージから始まる本作。しかし、冒頭で得られた感慨はオープニングナンバー「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」のキース・リチャーズのギターリフで見事なまでに掻き消される。伊達に何十年も王座に君臨しているバンドではない。数々のヒット曲で繰り広げられるルーズでタイトな貫禄のステージングが、すべての雑念を凌駕する。
もちろん、このステージ時がストーンズの全盛期ではない。映像に収められているセットリストで一番新しいナンバーは1983年(シングル盤リリースは1984年)の「シー・ワズ・ホット」であり、その他の大多数は1960、1970年代のナンバー。つまり完全なナツメロバンドである筈なのだ。にもかかわらず、この躍動する現役感は凄い。
更に驚くべきは、このコンサートを演じるストーンズの年齢だ。最年長のドラムス、チャーリー・ワッツの65歳を筆頭に、ミック63歳、キース62歳、途中加入のメンバーで一番若いギターのロン・ウッドでさえも59歳である。この年齢で、これだけのパフォーマンスが出来るのは、この世のものとは信じ難い。
中でも元気なのがミックである。モンローウォークならぬミックウォークとでも呼ぶべき独特のステップは錆び付いていない。顔に刻まれた深いシワなど無頓着に、若々しく艶やかに、そして挑発的に舞い続ける。
特に圧巻なのは終盤に訪れる「悪魔を憐れむ歌」だ。会場全体がミサのような雰囲気に包まれ、ミックはさながら司祭のようにオーディエンスをストーンズの魔力で扇動する。
豪華なスポットゲスト、ジャック・ホワイト、バディ・ガイ、クリスティーナ・アギレラが花を添える。由緒ある会場のビーコン・シアターのムードも良い。そして何より、ローリング・ストーンズが未だに少年のように転がり続けるローリング・ストーンズであるのが最高だ。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★