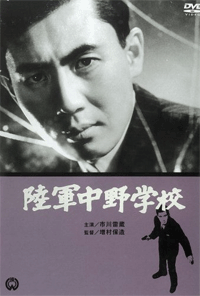
|
陸軍中野学校
1966 日本 96分 |
||
|
監督/増村保造
出演/市川雷蔵 加東大介 小川真由美 ピーター・ウィリアムズ |
|||
| 昭和13年10月、婚約者の雪子(小川真由美)の貯金で仕立てた軍服を着た三好次郎(市川雷蔵)は、母の菊乃(村瀬幸子)と雪子に見送られて自宅を出た。 |
スパイの根本精神は誠だ
戦前・戦中に実在した大日本帝国陸軍のスパイ養成機関、陸軍中野学校を舞台に、青年将校がスパイへとなる経緯を描いた作品。
梨園出身で「眠狂四郎」など時代劇のイメージがある市川雷蔵にとっては異色となる作品。ただ、好評だったらしく、本作を皮切りに5作品製作されてシリーズ化している。
昭和13年10月、陸軍予備士官学校を卒業して少尉になった三好次郎は、参謀本部の草薙中佐に呼び出され、そこでテストを兼ねた面接を受けた。それから1週間後、次郎は陸軍省に出頭せよとの秘密の命令を受けるのだった。その命令を受けた次郎を含めた18人の陸軍少尉は、九段の軍人会館の隣、愛国婦人会本部の中にある木造2階建てのバラックに集められる。そこで彼らは、草薙から18人を集めた主旨を初めて聞かされた。彼ら18人は、そのバラックで1年間、スパイになる教育を受ける為に集められたのだった。
本作が、どのような経緯で製作されたのか私は知らない。ただ、本作の製作年を考えれば、大ヒットしたスパイ映画007シリーズが念頭にあったのは間違いないだろう。但し、念頭にあるのと影響を受ける、あるいは倣うのとは違う話。本作は007路線を踏襲していない。
007と真っ向勝負するのは明らかに分が悪い。あのスタイルそのままに、少なくとも当時の日本映画が太刀打ち出来るとは到底思えず、もしも踏襲したのならば粗悪な二番煎じだと思われるのが関の山であっただろう。よって007とは違う道を選んだ事は賢い判断だったと私は思う。
但し、違う道を選んだからといって成功するとは限らない。オリジナリティーは主張出来るだろうが、結果が伴わず、完成した作品のクオリティーが低ければ粗悪品でしかない。しかし本作では、その心配は杞憂である。独自性は確保しつつ、高いクオリティーも誇っていると言えるだろう。
本作の上手さは、時代を遡り史実に拠り所を求めた点であるだろう。日本を囲む国際情勢が緊迫し、第二次世界大戦が目前に迫った時代が舞台となる本作。その時代の緊張感は日本人なら誰もが潜在的に想像出来るのではないかと思う。そんな時代のスパイを描こうとする発想力、着眼点が素晴らしい。
その時代を舞台にした事で顕著に感じるのは公私の分け目での個人の意識だ。現代でも個人的な生活を投げ打って仕事に打ち込む人はいるだろう。だが、その度合いは本作で描かれているものとは比べ物にならないのではないかと思う。
本作の若者たちが持つ職業意識は徹底している。親、兄弟、恋人、友人等との関係を含めた、それまでの人生すべて、更には戸籍、名前さえも抹消しなければならない程に過酷なのである。
スパイとは、そういうものなのかも知れない。だが、その運命を潔く受け入れる姿勢は時代が大きく関係しているように思う。しかも、観る者誰もが時代が行き着く先を知っている。なので、人生を捧げてまで未来を信じて働く姿は自然と哀愁を帯びてくる。
また、主人公の描き方も時代を映し出しているように感じる。雷蔵が演じる主人公は、もちろん主人公なのでクローズアップされ、主として物語が展開して行くのだが、こと集団の中では主人公とは思えぬ程に埋没している。
それは物語にメリハリをつける為の演出なのかも知れない。ただ、個人、しかも主人公を集団に飲み込ませる事で、個人的な信条だけではなく、時代の大流がそうさせるのだと感じさせる策を採っているのではないかと感じるのである。
興味深いのはスパイになる為の訓練の様子だ。もちろん「陸軍中野学校」と題するくらいだから訓練の描写があって当然なのだが、スパイ映画は数多くあれど、訓練の様子が描かれている作品は珍しいのではないかと思う。また本作とは関係がない007を持ち出して恐縮なのだが、訓練のカリキュラムを見ると007を作り出そうとしているようで何だかニヤけてしまう。
もっとも、よくよく考えてみれば007シリーズとはスパイエンターテインメントの帝王であるかもしれないが、それ故にスパイを描く上では本来あるべき姿ではないと言えるだろう。スパイとは日陰の存在であり、派手とは縁遠い存在である筈。つまりゴージャスな007とは対極にあるのがスパイの日常ではないかと思う。
身を粉にして国に仕えるスパイを、その成り立ちから丁寧に分かりやすく描いた本作はスパイ作品の本来の醍醐味を強く感じさせる。そんな本作が用意した非情な結末はスパイ稼業の、ひいてはその時代の過酷さを如実に表している。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★