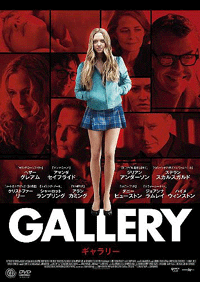
|
ギャラリー
2010 イギリス 94分 |
||
|
監督/ダンカン・ウォード
出演/ジリアン・アンダーソン ダニー・ヒューストン ステラン・スカルスガルド |
|||
| エレイン(ジェイミー・ウィンストン)への怒りを打ちまけながらアパートの階段を降りるジョニー(メレディス・オストロム)。その様子をビデオアートだと言ってビデオカメラで撮影するエレイン。そんなやりとりをしながら2人が建物の外に出た時、ドスンと大きな音がした。 |
これのどこが芸術なんだ
ロンドンのアート業界を舞台に、様々な思惑が入り交じる人間模様を描いた作品。原作はダニー・モイニハンの小説。モイニハンは本作の脚本も手掛けている。
原題は「Boogie Woogie(ブギウギ)」。これはオーストリア出身の画家ピエト・モンドリアンの絵画作品に由来している。
その絵画は確かに本作に登場するし、本作のポイントにもなっている。だが本作は、その絵画にまつわる物語という訳ではない。考え方によっては、その絵画の行く末が本作が発したメッセージだと受け取る事も出来るのだが、物語の構成上、今ひとつピントが不十分で、シンボルとするには弱い気がする。
一見すると、あまり面白味のない日本語の作品タイトルのように思えるのだが、作品内容を鑑みれば、中々賢明な作品タイトルの掛け替え作業が行なわれたと思う。
ロンドンでギャラリーを経営するアートは、ピエト・モンドリアン作の絵画「ブギウギ」を手に入れようと画策していた。「ブギウギ」の所有者はラインゴールドという老人。ラインゴールド家は家計が切迫しており、次々と所有する美術品や宝飾品を売りに出す有り様なのだが、モンドリアン本人から直接「ブギウギ」買い、それ以来ずっと所有しているラインゴールドに、「ブギウギ」を手放すつもりは断じてなかった。一方、アートの顧客でアートコレクターのボブは、アートの下で働く女性ベスが独立して自分のギャラリーを持とうと密かに目論んでいるのを支援していた。ボブは、アートのギャラリーのベスのオフィスに訪れた際、「ブギウギ」の情報を知るのだった。
本作は登場人物が非常に多い群像劇である。であるならば、ややもすると複雑で難解、あるいは逆に、まとまりなく散漫な印象を与える可能性もあると思うのだが、そういった過ちを本作は犯していない。
本作の登場人物たちは大旨、強烈な利己主義者である。そうする事で人間関係を希薄にし、物語の複雑化、難解化を回避している。ただ、それでは散漫な物語になってしまうだろう。そこで、明確で絶対的な芯を作り、その芯を囲むように登場人物たちを配置させている。そして、その芯に求心力を持たせる事で統一感を与えている。
この巧みな形態が抜群に機能しているので、雑多な群像劇でありながらも実に見やすい造りになっている。そして何より、この形態が美味なドラマを生み出している。
本作の芯とはアートである。登場人物たちが芯、すなわちアートを取り囲むように配置しているというのは、皆が同じ立場でアートに接している訳ではないという意味である。
アートを取り囲む人間にはアーティストもいれば、アートディーラーもいてアートコレクターもいる。つまりアートを、それぞれ自分なりの角度から捉えて愛しているのである。しかも、それぞれ個々のキャラクターは濃く、背景も違う。なので乗算で広がるような人間模様が映し出されている。
但し彼らには、おおよそ共通するものがある。それは何よりもアートを称え、アートの素晴らしさを最優先に生きている点である。彼らはアートの魅力に屈服し、アートの求心力に服従している人たちなのである。
何をも差し置いてアートに夢中になる彼らは純粋である。しかし、純粋であるが為にアートの為には平気で人を裏切るし傷つける。つまり彼らは、無条件でアートを愛する純真な心を持つ一方で、人として大切なものが欠落している人たちなのである。
そんな人たちが主導する物語は異様な様相を呈している。ヘザー・グラハムやアマンダ・サイフリッドらが時に官能的に物語を彩るが、それは目に見える氷山の一角。本作は、そもそもの本質が卑猥であり、イカれた人々が繰り広げる物語なのである。そして、その事を通じて結局は、アートとは何か?というところまで問いかけているように感じる。
本作はコメディーである。但し、抱腹絶倒するような明快なコメディーではなく、物事に対して斜に構えて嘲笑するようなコメディー、笑うに笑えない事も多々ある、どぎついユーモアで黒く塗り固められたコメディーである。こういったセンスはイギリス作品らしいと言えるだろう。
どうやら本作は日本では劇場公開されなかったらしい。本作に限った事ではないのだが、日本未公開という事と作品に対する評価は関係ない筈。しかし、日本未公開という事実がネガティブに作用し、作品が過小評価されてしまう場合も往々にしてある事だろう。
クセの強い内容であるのは間違いないので、見る人を選ぶのかも知れない。だが、中々の見応えを感じさせる作品ではないかと思う。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★