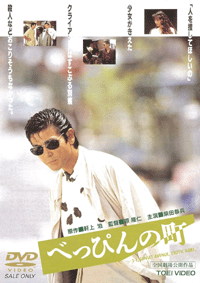
|
べっぴんの町
1989 日本 103分 |
||
|
監督/原隆仁
出演/柴田恭兵 田中美佐子 本木雅弘 笑福亭鶴瓶 |
|||
| 古いオープンカーに乗った男(柴田恭兵)がプールバーの前に車を駐め、若い男が写った写真を手に店内に入る。ビリヤードをしている写真の男を見つけると近寄り、「横田健次か? ちょっと話があるんだ。もう終わりにしろ」と言って、打とうとしている手玉を指で転がした。 |
また俺を呼べばいいんじゃない?
神戸を舞台に人捜しに奮闘する探偵の姿を描いた作品。原作は軒上泊の小説。小説はシリーズ化されているのだが、その1作目を映像化したのが本作。軒上泊は少年院で法務技官をしていた事があるようで、その影響が本作から伺える。軒上泊は映画「サード」の原作者でもある。
元少年院の教官で今は探偵をしている男は、通っているクラブのホステスで好意を寄せる女性、亜紀子と食事をしている時に亜紀子から人を捜して欲しいと頼まれる。尋ね人はクラブの常客の中嶋パールの社長の16歳の娘。家出をして1週間が経つという。亜紀子の勤めるクラブで中嶋パールの社長と面談し、男は正式に依頼を引き受ける事にした。その帰り道、男は尾行されている事に気付く。
探偵作品には、いくつかのジャンルがあり、その中で本作はハードボイルドな探偵作品だと言える。ハードボイルド探偵の特徴として挙げられるのは、事件を頭脳で解決するというよりも、行動で解決する点。なので、ミステリーの観点からすると少々、物足りなさを感じる場合も時としてある。
ただ、探偵の行動には危険を伴う事が往々にしてあり、それ故にスリリングな展開が構築される。それはミステリーだけに特化した作品とは違う魅力となる。そして何より、危険を顧みずに立ち向かう勇気、大きな困難を乗り越え、任務を遂行する強い精神力と肉体、そんな探偵のキャラクターや生き様こそがハードボイルド探偵作品の最大の魅力ではないかと思う。
だが、スマートフォンが広く普及した昨今では、靴底をすり減らさなくても、ソファーでくつろぎながら多くの情報が得られるようになった。そんな状況を踏まえるとハードボイルド探偵は、もはや過去の産物になってしまったのかも知れない。言い換えれば、ハードボイルド探偵を描くとしたら、時代を遡る必要があるのかも知れない。
ただ、面白い事にスマートフォンもインターネットも存在しなっかった1989年公開の本作においても、すでに懐古趣味は垣間見れる。主人公はライターではなく、マッチを擦ってタバコに火をつけ、愛車もクラシカルなメッキバンパーが装着された英国車MGB。こう至った背景は、1980年代のレトロブームがあるのは確かだ。だが一方で、往年のハードボイルド探偵へのリスペクトを感じ取る事も可能だ。
ハードボイルド探偵のイメージは、すでにハードボイルド探偵の黎明期に確立し、確固たるものになったと言えるだろう。ビジュアルに関して言えば、1940年代のスクリーンの中のハンフリー・ボガートのイメージだ。だが、さすがに中折れ帽とトレンチコートを着込んでしまうとコスプレの如くなってしまう。そこで、いくつかクラシックを散りばめ、往年のハードボイルド探偵のイメージを匂わせるといった手法を取る。これは本作に限った事ではなく、他の作品でも見受けられる定番の手法だと言える。ちなみに、本作の主人公は氏名を明かさないのだが、これはハードボイルド探偵の元祖と称されるダシール・ハメットの小説「血の収穫」(または「赤い収穫」)が念頭にあったと推測できる。
他方、懐古趣味は作中では、主人公のライフスタイルの一環として描かれている。それは、もちろん単純に主人公の趣味嗜好であり、センスだと考える事ができるのだが、もう少し深読みすれば、世間や時代に流されないという主人公の意志、生き方だと捉える事もできないだろうか。懐古趣味はタフなハードボイルドの精神を表現しているようにも感じる。
本来、ハードボイルドはシリアスなものであるが、日本では、例えば、松田優作主演のテレビドラマ「探偵物語」のような、ユーモアやコミカルさを兼ね備えた通俗ハードボイルド、あるいは軽ハードボイルドと呼ばれるハードボイルドが人気だと感じるし、中には通俗、軽ハードボイルドを本格的なハードボイルドだと勘違いしている人もいるように思う。その通俗、軽ハードボイルドの名プレーヤーが本作の主演、柴田恭兵だ。
本作は原作の小説に比べて格段にスタイリッシュになっている。その要因は柴田に他ならない。ただ、本作で柴田は幾分、抑えた演技をしており、通俗、軽ハードボイルド感は薄い。少し残念な気もするのだが、作品内容や主人公の経歴、キャラクターに即した演技をしていると言える。柴田のハードボイルドには違う引き出しがあったのだ。と同時に、柴田が次のキャリアに進む事を予見しているようにも感じる。
柴田の演技の特徴の1つとして、怒鳴る演技の上手さを挙げたい。怒りを表現する際や何か大切な事を伝える時等に声を荒げる、という演技が行われる場合が度々あると思うのだが、難しいのだろうか、ベテラン俳優や名優の誉れを得ている俳優であっても、迫力不足、説得力不足だと感じる事が多々ある。その点、柴田は表現すべき感情と実際に表現した大きな声とが見事なまでにイコールで結ばれている。見栄えも良い。これは柴田の非常に秀でた点だ。舞台出身という事が関係しているのだろうか。
また、これは柴田の演技という話とは少し違うのであろうが、柴田の運転シーンにも注目したい。ステアリングのダイレクト感、カクッ、カクッと音を奏でるシフトレバー。カメラを搭載した車両がオープンカーなだけあって、視界は開けていて、臨場感は抜群。決して過言ではなく、運転シーンも本作の見どころの1つだと推奨したい。
柴田の相棒を本木雅弘が演じる。所属していたアイドルグループ、シブがき隊が解散したのが本作公開の前年なので、本作は本木が俳優業に本腰を入れ始めた頃の作品となる。そんな事情が影響しているのか、正直、本作での役柄は本木には似合わない。だが、本木は自身の個性に役柄を引き寄せる事で、似合わない役柄を上手に着こなしている。こういったところでも本木のセンスやインテリジェンスを察する事ができる。また、本木がいる事で作品が華やいだのは間違いない。
ヒロインは田中美佐子。ミステリー作品のヒロインは作品の行方に深く関わる重要な役割を担っている。その重責を田中は自身の実力で見事に果たした。本作での田中は、落ち着きのある大人の香りを漂わせつつ、可愛らしさや親しみも感じさせる。それでいて、どこか寂しくて儚い。田中は1990年代に入ると立て続けにテレビドラマの主役を務める事となるが、本作においても田中の魅力は大いに実感できる。
和久井映見も田中同様に1990年代にブレイクした女優だ。但し、田中と異なるのは本作公開当時、まだキャリアの浅い新人女優だった事。にもかかわらず、自然な演技で作品に馴染んでいる。更に驚いたのは、年齢とキャリアを重ね、ベテランの域に達しても、大きくイメージが変わっていない事だ。和久井の輝きは、すでに本作の時点で放たれている。
そして、つみきみほにも言及したい。つみきの個性は他に類を見ない程に異質。その上、演技に肝が据わってるので抜群の存在感を示す。だから、そこには1つの世界ができてしまう。稀有な才能の持ち主だ。
最後に、1995年(平成7年)の1月17日に阪神・淡路大震災が発生し甚大な被害をもたらしたのだが、本作には震災前の風景が記録されている。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★
おすすめ映画情報-シネマメモ