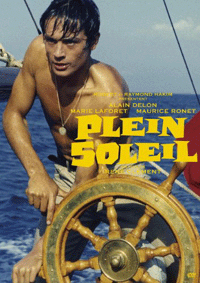
|
太陽がいっぱい
1960 フランス/イタリア 118分 |
||
|
監督/ルネ・クレマン
出演/アラン・ドロン マリー・ラフォレ モーリス・ロネ |
|||
| ローマのカフェにいるトム(アラン・ドロン)とフィリップ(モーリス・ロネ)の元にフレディ(ビル・カーンズ)が現れた。フレディはフィリップの友人。だが、トムとフレディは互いに良い印象を持っていなかった。 |
俺は他人の金で遊んでる
原作はパトリシア・ハイスミスの小説。虐げられていた青年が犯す罪の顛末を描いた作品。
本作はアラン・ドロンの出世作であり、代表作の1つに数えられる作品である。本作以降、ドロンの出演作の日本語タイトルで「太陽」や「いっぱい」が使われるのは、おそらく本作の影響であるだろう。それだけ当時、強烈なインパクトを残した作品だったのだと思う。
放浪している息子のフィリップをサンフランシスコに連れ戻すようにと、フィリップの父親から5000ドルで頼まれたトムは、アメリカから遥々ヨーロッパへと出向いていた。だが、フィリップは帰るつもりはなく、トムもフィリップに面倒を見てもらって遊び回る生活が、まんざらではなかった。フィリップとトムは昔からの知り合いであり、一見すると友人のような間柄なのだが、裕福なフィリップと貧乏なトムとの間には絶対的な主従関係が成り立っており、フィリップはトムを見下していた。フィリップには婚約者のマージュという女性がいて、フィリップとマージュ、そしてトムの3人は、イタリアのタオルミナにフィリップのヨットでバカンスへと出掛ける事となった。航海中の船上でフィリップのトムへの態度はエスカレートする。自分を邪険に扱うフィリップに対し、トムは憎悪を募らせていた。
本作はブルジョアとプロレタリアとの間に生ずる確執がベースに描かれている。確執の原因は、傲慢なブルジョアの優越感と服従するプロレタリアの劣等感。ヒューマニズムに背いた関係に、弱者であるプロレタリアが反旗を翻す事で物語は大きく動く事となる。
但し、健全なカタチで反旗を翻した訳ではない。プロレタリアはブルジョアが支配する封建的な関係を打破して、自身の階級の権利を掴もうとするような大儀のもとに行動を起こしたのではなく、ブルジョアに憧れ、自身もブルジョアに成るべくして行動を起こしたのである。人を人とは思わない傲慢なブルジョアは悪党だが、汚れた野心を抱え、非道な行為に走るプロレタリアも同類である。
これだけの有り様であれば、酷く不快な物語であっただろう。原因が原因だけにプロレタリアに同情心は芽生えるのかも知れない。しかし、悪質極まる行動を考えれば、とてもじゃないが共感は出来ない。だが、ここでドロンのキャスティングが効力を発揮するのである。
ドロンが演じる事によリ、極悪なプロレタリアはアンチヒーローとなった。もちろん、利己主義のみによって積み重ねられる悪事の数々が正当化される筈もない。しかし、ドロンの色香という魔力により、正当化も共感も出来ずとも、自然と意識が極悪なプロレタリアに同調する事となる。
その同調性こそが、本作の特色である手に汗握るスリリングなサスペンスを生み出している。正常な感覚を惑わせる圧倒的なドロンの魅力。本作でのブレイクは納得出来るだろうし、また、その後の活躍も本作を観れば理解出来るだろう。
本作には、ホモセクシャルが描かれているという説がある。確かに、その説を適用すれば、更に物語は深みを増す事だろう。だが、残念ながら私には、その説を本作から読み取る感性がなかった。しかし、それでも存分に楽しめた作品であり、未だに色褪せない傑作であると思う。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★