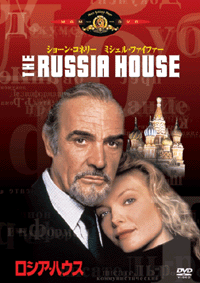
|
ロシア・ハウス
1990 アメリカ 124分 |
||
|
監督/フレッド・スケピシ
出演/ショーン・コネリー ミシェル・ファイファー ジェームズ・フォックス |
|||
| モスクワで開催されているイギリス・オーディオ・フェアに訪れたカーチャ(ミシェル・ファイファー)。目的はバーリー(ショーン・コネリー)という男に、ある原稿を渡す為だった。しかし、バーリーは不在、モスクワにすら来ていなかった。困ったカーチャは、その会場にいた出版セールスマンのニキにバーリー渡して欲しいと原稿を託すのだった。 |
君はグレイを着ている
原作はジョン・ル・カレの小説。東西冷戦末期、共産党崩壊直前のソ連を舞台にしたスパイ活動を描いた作品。
スパイ作品と聞けば、ショーン・コネリーの代表作である007シリーズが思い浮かぶ。そのシリーズの中には「ロシアより愛をこめて」なんて作品も存在する。また、正規のシリーズではないのだが、同じく007作品の「ネバーセイ・ネバーアゲイン」に悪役として出演しているクラウス・マリア・ブランダウアーが本作でキーとなる役を演じている。
そういった事を踏まえてみると、本作が007シリーズと同じような作品なのではないかと想像してしまうのは当然の成り行きであろう。実際、ショーン・コネリーの持つジェームズ・ボンドのイメージを利用している面は大いにあるのだと思う。
だが、本作は007シリーズとは、ある意味対極な作品であると言って良いだろう。本作にアクションシーンは皆無。また、女性に対する扱いもジェームズ・ボンドとは根本的に大きく異なる。
ストーリーのきっかけとなるのは、ショーン・コネリー演じるイギリスの出版社社長バーリーに宛てられた原稿。その原稿は、バーリーの元に届く前に開封され、イギリス諜報部に渡ってしまう。原稿にはソ連の機密事項が記されていた。最初は原稿に覚えがなかったバーリーだが、記憶を辿ると、ロシアのペレデルキノという村で出会ったある男の存在が思い出される。そこでイギリス諜報部は、民間人であるバーリーをスパイとして潜入させる作戦を立てる。
民間人をスパイとして潜入させるなんて、通常なら現実離れした設定に感じるであろう。だが、あながちそうとは言い切れないと感じさせるのが本作である。
国益や世界平和といった大義の前では、それが良いか悪いかは別にして、本来なら守られるべき法律や人権はどこかに追いやられてしまうのかも知れない。そのような思考に陥ってしまうのも、緻密で優れたストーリーと演出、そして俳優たちの巧みな演技があるからこそである。
本作で大きなポイントとなるのは、崩壊寸前のソ連が舞台になっている点だ。現在もカタチを変えて残っているとも言えるが、イデオロギーの違いが直ちに善と悪に置き換えられていた東西冷戦の時代。しかし、その時代が終焉を迎えようとしていた本作の舞台となる時期では、その常識も綻びを見せる。
いつの時代も体制に反旗を翻し志しを貫く者はいるのであろう。だが、史実としてダイナミックに時代が動く不安定な情勢の中では、その姿は生々しいリアリティーを感じさせる。
さらには、そのリアリティーはイギリスとアメリカの両国間の関係性の描写にも感じられる。それが覇権争いなのか、国力に物を言わせた力関係なのか、はたまた手柄を自らのものにしたい欲なのかは分からないが、両国の諜報機関の間に微妙な空気が流れている。同盟を結んでいる同士の不穏な内部事情もリアリティーの構築の一翼を担っていると言えるだろう。
とにかく良く出来たストーリーである。激動の時代を反映させつつ、見通しをつかせずに多岐に渡って展開されるストーリーは充実感で一杯である。と同時に実に渋い作品でもある。質実な作風もさることながら、その渋みに大きな影響を及ぼしているのはショーン・コネリーである。
ショーン・コネリーが演じるバーリーは、一民間人の素人スパイであり、007のようなスーパースパイには到底成り得ない。だが、バーリーには歩んできた人生で彫り込まれた年輪がある。なので、単なる使い走りでは終わらない。そんなキャラクターに恰好がつくのもショーン・コネリーの存在感なのだと思う。
若々しいジェームズ・ボンドの姿もカッコ良いのだが、年齢を重ねたショーン・コネリーの枯れ具合も若い時とは違った味わいを感じさせ、大変色っぽく魅力的だ。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★