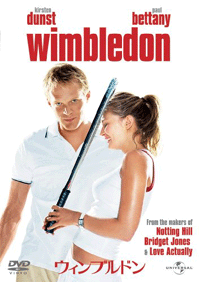
|
ウィンブルドン
2004 イギリス/フランス 99分 |
||
|
監督/リチャード・ロンクレイン
出演/ポール・ベタニー キルスティン・ダンスト |
|||
| 落ち目のプロテニスプレーヤーのピーター(ポール・ベタニー)はテニスクラブのコーチの職の依頼を受けており、全英オープンテニス(ウインブルドン)を最後に現役を引退する決意をしていた。ウインブルドンの為に滞在するホテルで部屋を間違えたことにより女子プロテニスプレーヤーの有望選手のリジー(キルスティン・ダンスト)と知り合うのだが… |
スポーツマンらしく爽やかな恋愛物語
落ち目の男子プロテニスプレーヤーと新進気鋭の女子プロテニスプレーヤーの爽やかなコメディタッチのラブストーリー。
何気なくちりばめられたジョークやユーモアが良いエッセンスとなっている。ジョーク・ユーモア自体が面白いか否かというはもちろんなのだが、何時・何処でどうすればジョーク・ユーモアを効果的なのか? というのが案外大切なのだと思った。別にそのジョーク・ユーモアでドカンと笑いを取らなくても良い。潤滑油のようになれば良い。笑うのではなくニヤっとするぐらいで良い。この加減はもしかすると日本人には不得意な分野なのかもしれない。それは日本映画の制作者側にそのセンスがないのではなく、残念ながら日本人全体にそのセンスが乏しいのではないかと思う。
スポーツを題材にした作品は難しい。スポーツにドラマを感じるの大きな要素は、技術・精神等の向上といった努力のプロセスと試合での緊張感・臨場感だと思う。しかし映画で努力のプロセスを描くには時間が少なすぎるし、試合での本当の緊張感・臨場感というのは容易く描けない。本作では落ち目のベテランプレーヤーを主役にしていることが良い効果を与えている。プロの世界は紙一重なのだと思う。そう考えればちょっとしたことで調子を取り戻し好成績を得ることはあるのだと思う。そうであれば努力のプロセスを描く必要がない。さらにはウィンブルドン大会の期間中という限られた時間の設定も努力のプロセスを描く余地を省き散漫にならない効果をもたらしている。
正直に言うと本筋はオーソドックス。しかし巧みな設定と味付けで結局は本筋に引き込まれていく。物語への高揚は自然とクライマックスシーンの試合の緊張感・臨場感とリンクしていく。スポーツ作品をつまらなくさせない、上手く考えられた構成であり演出だと思う。
落ち目ではあるが悲愴感を感じさせないピーターをポール・ベタニーが爽やかに演じ、逆にアスリートらしい野心を持った若きリジーをキルスティン・ダンストが可愛らしく演じている。ピーターの弟を演じるジェームズ・マカヴォイをはじめ脇役陣もいい味を出している。
>>HOME
>>閉じる
★前田有一の超映画批評★
おすすめ映画情報-シネマメモ